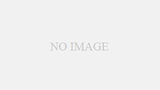ジエチルエーテルとは聞きなれない名前ですが、危険物第4類に分類される危険物。
危険物第4類を取り扱える危険物取扱者乙種第4類は、最も受験者数も多いでしょう。
そこで、今回はこのジエチルエーテルの性質や特徴をご紹介します。
危険物乙種第4類は社会人にも人気の資格です。
ですから、受験者も多いでしょう。
今回は、受験勉強のコツなどもご紹介します。
これから危険物乙種第4類を受験したいという方も、ぜひこの記事を読んでみてください。
- ジエチルエーテルの性質や特徴とは?
- ジエチルエーテルを取り扱う際の注意点
- ジエチルエーテルが発火したら?
- 危険物乙種4類の特徴
- おわりに
1.ジエチルエーテルの性質や特徴とは?
ジエチルエーテルとは、危険物乙種第4類に分類されている物質で無色透明の液体です。
危険物とは、消防法によって定められた物質の総称のこと。
不用意に取り扱ったり保管したりすると爆発や発火の危険があるので、保管方法や取り扱い方に決まりがあります。
危険物にはそれぞれ指定数量があり、指定数量を超えた危険物を取り扱ったり保管したりするには「危険物取扱者」という資格が必要です。私たちの最も身近にある危険物取扱者の資格取得者の専任が必要な施設は、ガソリンスタンドになります。
さて、ジエチルエーテルは危険物第4類に分類されているのです。
危険物は、その性質や特徴で第1類~第6類に分類されています。
危険物第4類は「引火性液体」つまり、火を近づけると燃えやすい液体が指定されているのです。
ジエチルエーテルは、第4類中でも最も引火点が低く⁻45度で火がつきます。
つまり、冷凍庫の中でも火の気を近づければ発火するのです。
そのため、必ず火気厳禁で保管しなければなりません。
ジエチルエーテルは、現在燃料として補助的に使われているほか、有機金属化学の溶剤として使われています。
また、学校の研究所などに少量保管されていることが多いです。
取り扱いには十分注意してください。
また、ジエチルエーテルは熱すると有毒な蒸気を発生し、比重が水よりも軽いという特徴もあります。
2.ジエチルエーテルを取り扱う際の注意点
ジエチルエーテルは、前述したように引火点が第4類危険物の中では最も低いです。
引火点とは、火気を近づけると発火したり爆発したりする温度のこと。
みりんやお酒を熱したものにマッチの火を近づけると炎が出るのは、引火点に達したからです。
また、何もしなくても自然に火がつく温度を「発火点」といいます。
油を熱し続けると火柱が上がるのは、発火点に達したからです。
ジエチルエーテルは、常温でも火種を近づけると発火します。
マッチやライターの火はもちろんのこと、静電気にも注意が必要でしょう。
また、熱すると麻酔性の蒸気を発生します。
ですから、冷却装置などで沸点以下にして管理するのです。
さらに、蒸気が発生しないように熱を加える際は100度以下の温度をたもち、通気をよくしましょう。
そして、保管する容器は鋼製のものを使用します。
これは、銀や銅の容器に入れると爆発性の化合物を生成する恐れがあるためです。
3.ジエチルエーテルが発火したら?
この項では、万が一ジエチルエーテルが発火した場合の対処法をご紹介します。
取り扱っている場所に勤務している方は、ぜひ覚えておいてください。
3-1.ジエチルエーテルの危険性
ジエチルエーテルは、電気の不良導体であるため非常に静電気が発生しやすいのです。
ですから、冬場に帯電しやすい方が不用意に触るとその静電気で発火することもあるでしょう。
また、ジエチルエーテルの発火点は160度です。
ですから、熱した器具などにジエチルエーテルの飛沫(ひまつ)がかかれば、すぐに発火してしまう恐れもあります。
ですから、取り扱う際も熱したものの近くに置かないようにするなど、注意を払いましょう。
3-2.ジエチルエーテルの消火方法とは?
危険物第4類は、水よりも比重が軽いものが多いです。
そのため、水をかけるとかえって燃えている場所が広がってしまうこともあるでしょう。
しかし、ジエチルエーテルの場合は水による冷却消火が有効です。
また、二酸化炭素や泡による窒息消火も行えます。
ただし、ジエチルエーテルは気体になると、麻酔性の蒸気が出るのです。
これを直接吸引すると、最悪の場合意識を失います。
ですから、不用意に燃えているところへ近寄らないように注意してください。
3-3.消防を呼ぶ際の注意点
ジエチルエーテルに限らず、危険物に引火した際は必ず危険物取扱者の資格保有者が消防に通報しましょう。
その際、どのような危険物がどの位の量で燃えているか報告してください。
そうすれば、消防署員が設備を整えて消火に来てくれます。
また、必要ならば危険物取扱者が先頭に立ってその場にいる人を避難させましょう。
ジエチルエーテルは爆発の危険こそありませんが、麻酔性のガスを多量に吸いこむと体によくありません。
風向きや発火している量によっては近隣の住民も避難させる必要があります。
4.危険物乙種4類の特徴
この項では危険物乙種4類に分類されている物質の特徴をご紹介します。
受験勉強にも役に立つのでぜひ目を通してみてください。
4-1.引火性液体とは?
引火性液体とは、文字どおり火を近づけると燃えやすい液体のことです。
最もイメージしやすいのは、ガソリンをはじめとする燃料や油でしょう。
実際、引火性液体に分類されている危険物のほとんどが、石油製品です。
引火性液体は燃料や塗料、さらに食料として私たちの身近にたくさん存在します。
ですから、それを取り扱う危険物取扱者も需要が高いのです。
4-2.引火性液体の分類の方法とは?
引火性液体は、危険物の中でも特に種類が多いでしょう。
ですから、引火点ごとに分類されているのです。
引火点が低いほど危険性は高いと考えてください。
第4類危険物は、さらに特殊引火物と第1~第4石油類、アルコール類に分類されています。
その中で、最も引火の温度が低いのが特殊引火物です。
ジエチルエーテルも特殊引火物に分類されています。
ですから、それぞれの引火点を覚えておけば、物質同士がごっちゃになることもないでしょう。
また、分類された中にはそれぞれ代表的な物質があります。
第一石油類はガソリン、第二石油類は灯油と軽油などです。
これらは私たちの生活にも密着していますから、特徴や危険性も覚えやすいでしょう。
これをまず覚えてしまえば、ほかの物質も覚えやすいのです。
5.おわりに
いかがでしたか?今回はジエチルエーテルの性質や特徴をご紹介しました。
危険物第4類というとガソリンや灯油ばかりがクローズアップされますが、このような物質もあることを覚えておきましょう。
ジエチルエーテルは、かつて麻酔剤としても使われていました。
そのため、少量でも蒸気を吸いこむと意識が混濁する恐れがあります。
ですから、必ず風通しのよい場所で熱してください。
また、ジエチルエーテルを取り扱う場所の近くには、静電気除去装置を置いておくとよいですね。
ガソリンのように大容量を取り扱う機会は限られていますが、一度燃え出すと厄介でしょう。
また、ジエチルエーテルは冷却設備の中に保管されていることが多いですが、万が一を考えて必ず冷凍庫は防火設備のあるものを使用しましょう。
専門に取り扱っているメーカーもありますので、問い合わせてみてください。
不用意に家庭用のもので代用しないようにしましょう。